原因は環境やメンタルだけじゃない!
チックとは、目的のない不随意運動(運動チック)や、意図しない音や言葉が突然繰り返し発せられる現象(音声チック)です。チックは、意識的に努力することで短時間抑えることが可能ですが、完全に治すことは難しいです。トゥレット症候群は、運動チックと音声チックが1年以上続く場合に診断されます。
チックは通常、18歳までに発症し、特に4歳から6歳の間に見られることが多いです。症状は10~12歳頃に最も激しくなり、青年期に入ると減少する傾向があります。ほとんどのケースでは、症状はやがて収まりますが、約1%の小児では成人期まで残ることがあります。
チック症には主に3種類があります:
1.暫定的チック症:運動チックまたは音声チックが1年以内に見られる場合
2.持続性チック症(慢性チック症):運動チックまたは音声チックの片方だけが1年以上続く場合
3.トゥレット症候群:運動チックと音声チックの両方が1年以上続く場合
通常、暫定的チック症から始まり、場合によっては持続性チック症やトゥレット症候群に進行することがあります。
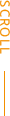








 車:12分
車:12分 徒歩:48分
徒歩:48分
